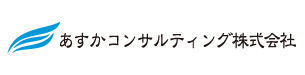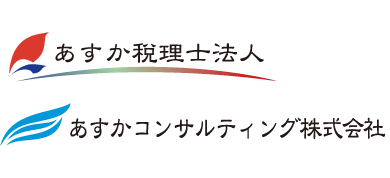BLOGブログ
会計・ファイナンス・監査2025.04.09 新しいリース会計基準について(その1)
既にご承知の方も多いと思いますが、2024年9月、企業会計基準委員会(ASBJ)は、「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号、以下「基準」)及び「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号、以下「適用指針」)を公表しました。今回から、シリーズでこの新しいリース会計基準の内容についてお話させて頂きます。1回目の今回は、会計基準が取り扱うリースとはどのようなものかを確認したいと思います。
※新しいリース基準の概要については、こちらもご覧ください。
1.リースの定義及び識別の判断
新しいリース会計基準において、リースは以下ように定義されています【基準.6】。
原資産(リースの対象となる資産)を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約または契約の一部分
ですが、新しいリース会計基準では、このリースの定義とは別に、リースを特定する(識別する)ための定めを置いています。
契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合に当該契約はリースを含むとされ【基準.26】、この資産を支配する権利が移転する場合の要件は、特定された資産の使用期間全体を通じて、次の①②のいずれも満たす場合であるとしています【適用指針.5】。
① 顧客が特定された資産の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを享受する権利を有する
② 顧客が特定された資産の使用を指図する権利を有する
この中で、「特定された資産」と「使用を指図する権利」という用語については、基準や適用指針において、詳細な記述がなされています。次は、この内容について、見ていくことにしましょう。
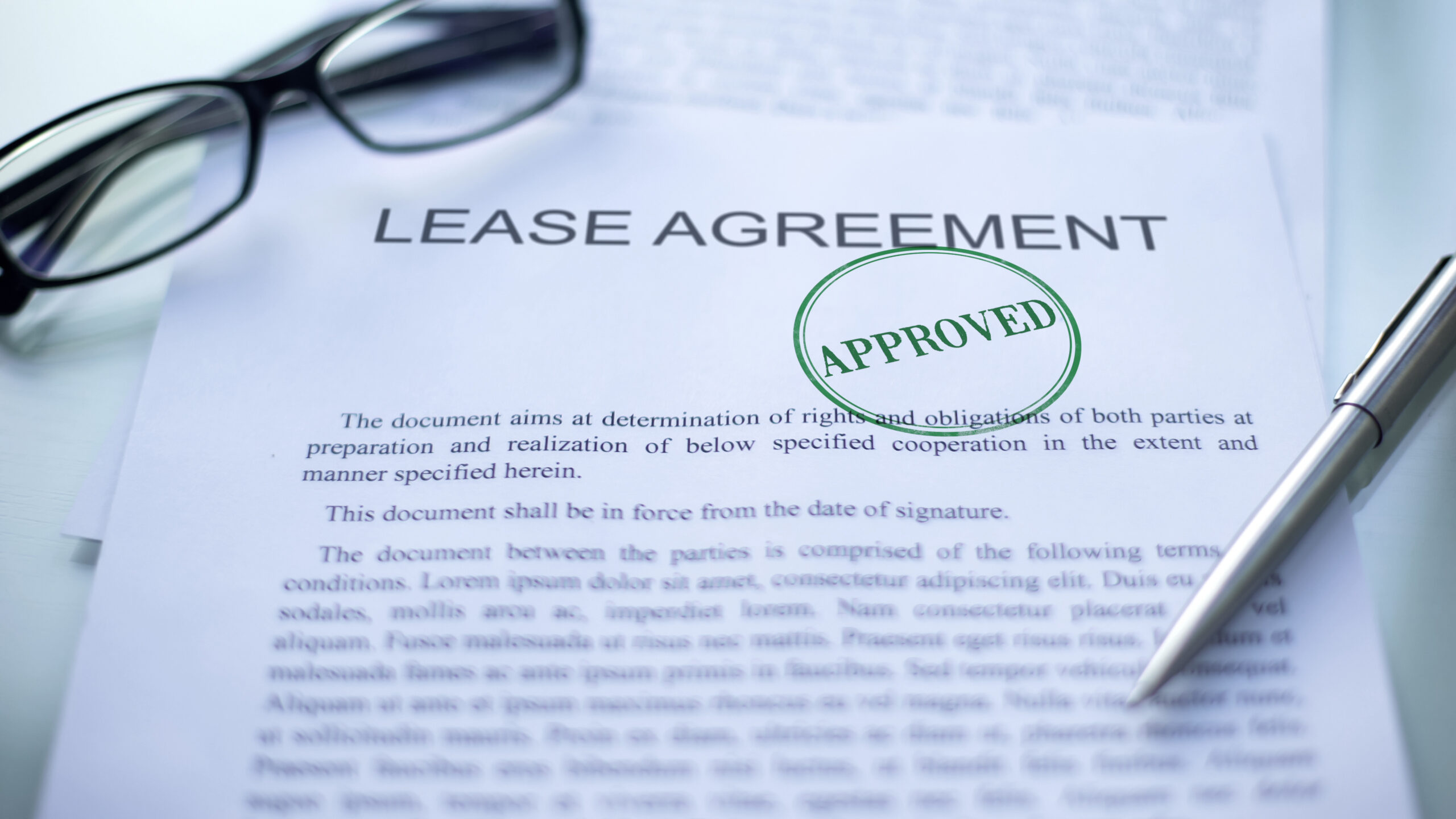
2.特定された資産
通常、(対象となる)資産は契約に明記されることによって特定されるとする一方で、資産が契約に明記されている場合であっても、次の①②のいずれも満たす場合は、サプライヤーが当該資産を代替する(対象となる資産を別の資産と交換することができる)実質的な権利を有しており、当該資産は特定された資産には該当しないとされています【適用指針.6】。
① サプライヤーが使用期間全体を通じて当該資産を他の資産に代替する実質上の能力を有している
※顧客はサプライヤーが資産を入れ替えることを妨げることができず、サプライヤーが代替資産を容易に利用可能であるか合理的な期間内に調達できる場合が該当するとされています【適用指針.BC11】
② サプライヤーにおいて、当該資産を代替することからもたらされる経済的利益が、代替することから生じるコストを上回ると見込まれるため、当該資産を代替する権利の行使によりサプライヤーが経済的利益を享受する
ここで、「顧客」と「サプライヤー」という言葉が使われていますが、これは、リースの識別の段階においては、その契約がリースを含むか否かを判断する段階であるために、敢えて「借手」「貸手」という用語を用いず、「顧客」「サプライヤー」という用語を用いているとのことです【適用指針.BC9】。
※「サプライヤー」が資産を提供する側(リースに該当すれば貸手)で、「顧客」が資産を使用する側(リースに該当すれば借手)と読んで頂くと理解しやすいのではないかと思います。
また、顧客が使用することができる資産が物理的に別個のものではなく、資産の稼働能力の一部分である場合も考えられますが、このような資産の稼働能力部分は特定された資産に該当しないとされています【適用指針.7(前段)】。
一方で、顧客が使用することができる資産が物理的に別個のものではないものの、顧客が使用することができる資産の稼働能力が、当該資産の稼働能力のほとんどすべてであることにより、顧客が当該資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している場合は、当該資産の稼働能力部分は特定された資産に該当するとされているため【適用指針.7(後段)】、注意が必要です。
3.使用を指図する権利
顧客は、次の①または②の場合にのみ、使用期間全体を通じて特定された資産の使用を指図する権利を有しているとされています【適用指針.8】。
① 顧客が使用期間全体を通じて使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法を指図する権利を有している場合
② 使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る決定が事前になされており、かつ、次のいずれかである場合
・使用期間全体を通じて顧客のみが資産を稼働する権利を有しているか、第三者に指図することにより資産を稼働する権利を有している
・顧客が使用期間全体を通じた資産の使用方法を事前に決定するように、資産を設計している
結論の背景においては、顧客が当該資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しているときには、顧客が当該資産の使用を支配する権利を有するため契約はリースを含むことになる一方、サプライヤーが資産の使用を指図する権利を有している場合、契約はリースを含まないという考え方が示されています【適用指針.BC12】。
ここまでの内容については、適用指針の中の[設例1]において、フローチャートの形で示されていますので、こちらも合わせてご確認ください。
4.リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分
上記のリースの識別に関する定めを考えると、実際には契約そのものがリースに該当する場合だけでなく、契約の中にリースの要素が含まれているような場合も考えられます。このようなリースを含む契約については、原則として、リースを構成する部分と構成しない部分に分けて会計処理を行うことが求められています【基準.28】。
借手が、契約における対価の金額について、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに配分するにあたっては、それぞれの部分の独立価格の比率に基づいて配分します【適用指針.11(前段)】。また、契約における対価の中に、借手に財・サービスを移転しない活動やコストについて借手が支払う金額が含まれる場合は、当該金額を契約における対価の一部としてリースを構成する部分とリースを構成しない部分とに配分します(当該金額を契約における対価からは控除しない)【適用指針.11(後段)】。
この際、リースを構成する部分とリースを構成しない部分の独立価格の算定をどのように行うかがポイントとなりますが、適用指針においては、以下のような方法が示されています【適用指針.BC18】。
・貸手または類似のサプライヤーが、企業に個々に請求するであろう価格に基づいて算定
・借手において、その独立価格が明らかでない場合、借手は、観察可能な情報を最大限に利用して、独立価格を合理的な方法で見積る
なお、原資産を使用する権利は、次の①②の要件のいずれも満たす場合、独立した(単独の)リースを構成する部分であるとされています【適用指針.16】。
①当該原資産の使用から単独で借手が経済的利益を享受することができるか、当該原資産と借手が容易に利用できる他の資源を組み合わせて借手が経済的利益を享受することができる
②当該原資産の契約の中の他の原資産への依存性または相互関連性が高くない
この定めは、IFRS第16号において、リースを含む契約が単一のリースを構成する部分が含まれるのか、複数のリースを構成する部分が含まれるのかを判定する定めが置かれているものを日本の新リース会計基準においても取り入れたものとなっており、収益認識会計基準における履行義務の識別とも整合的なものとなっているとされています【適用指針.BC26】。
以上が、ある契約において、リースを構成する部分とリースを構成しない部分が含まれている場合の原則的な会計処理ですが、以下のいずれかの区分ごとに、リースを構成する部分とリースを構成しない部分を分けずに両方をリースを構成する部分として会計処理を行うことを選択できるという定めが設けられています【基準.29】。
・対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表に表示する科目ごと
・性質及び企業の営業における用途が類似する原資産のグループごと
この基準.29の処理は、リースを構成する部分とリースを構成しない部分を分けて会計処理を行うコストと複雑性を低減しつつ、会計基準の開発目的を達成するための例外的な取扱いであり、また、リースを構成する部分とリースを構成しない部分を合わせて、リースを構成しない部分として会計処理を行うことは認められていないことに留意が必要です【基準.BC33】。
※IFRS第16号の結論の根拠では、この処理が選択されるのは、リースを構成しない部分が比較的小さい場合のみであることが想定されているようです。
(次回につづく)
あすかコンサルティング株式会社
【会計コンサルティング担当】津田 佳典
プロフィールはこちらをご覧くださいませ!