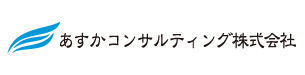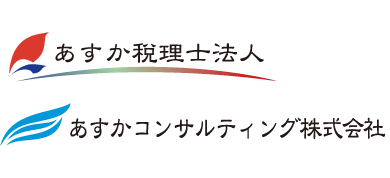BLOGブログ
会計・ファイナンス・監査2024.06.19 循環取引について考える(その1)
日本監査役協会、日本内部監査協会、日本公認会計士協会は、「循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告」(以下、研究報告)を公表しました。今回は、この研究報告を参考に、不正会計の手法の1つでもある循環取引について、考えてみたいと思います。
1.循環取引とは?
研究報告において、循環取引とは「複数の企業が共謀して商品の転売や役務の提供を繰り返すことにより、取引が存在するかのように仮装し、売上や利益を水増し行為の総称」と定義されています。
また、循環取引については、一般的に以下のような特徴があるとされています。
・通常の取引と同様に実在性を示す証憑が作成・保存され、証憑間の整合性が取れ、資金のやり取りも含めて偽装される
・実在する多数の企業や当事者が関与し、複雑な商流が作られることから、一度通常の取引として認識されると発見が困難な取引となる(このため、循環取引による不正は影響額が巨額になるケースが少なくない)
研究報告では、循環取引の形態について、以下のように整理されています。
・スルー取引
自社が受けた注文について、物理的・機能的に付加価値の増加を伴わず他社へそのまま回し、帳簿上通過するだけの取引(売上の水増しに使われる)
・Uターン取引(回し取引)
商品・製品等が、最終的に起点となった企業に戻ってくる取引のことで、複数の企業を経由する間に手数料等が上乗せされた状態で、商品・製品等が起点となった企業に還流される(巨額になった在庫が回せなくなった時点で不正が発覚するケースが多い)
・クロス取引(バーター取引)
複数の企業が互いに商品・製品等を販売し、当該相手方の商品・製品等を在庫として保有し合うか、在庫をせずに他の複数の企業に対して相互にスルーする取引
2.循環取引が示唆される状況・兆候
一度、通常の取引として認識してしまうと、発見が困難になるとされている循環取引ですが、循環取引を示唆する状況・兆候が、以下のように整理されています。
(1) 事業上の合理性が不透明な取引
仮装された取引であることから、事業上の合理性が不透明(=なぜ、その取引を会社が行っているのかの理由が不明確)な取引であることが多いとされており、具体的な事例として、以下のような特徴が示されています。
・同業他社から仕入れたものを同業他社に販売している
・通常取引を行うことが想定されにくい企業等から仕入れたものを販売している
・仕入先や販売先が、あらかじめ決まっているにもかかわらず、仲介を要請されて商流に参加している(商流に参加する理由が不明確)
・取引名が「○○一式」や「○○追加取引」等詳細が記載されていない
(2) その他留意すべき取引の特徴
また、循環取引は、その取引自体に特徴があることが多いともされています。
・直送取引、大型設備の仲介、倉庫での名義変更取引など帳票のみで自社の取引が完了し、モノの移動が捕捉しにくい取引である(このような取引を行うことが珍しい場合は、疑ってみた方がいいかもしれません)
・エンドユーザーまで複数の会社が介在し、エンドユーザーが不明確である
・技術やソフト、サービス等、その価値を第三者が客観的に判断することが難しい(このため、循環取引が発生しやすい業界も存在します)
・1つのプロジェクトにおいて、原価の内容のほとんどが外注費で、しかも特定の外注先に依存している(これは、明らかに不自然な取引ですね)
・取引先に対して優越的な地位にある場合、取引先を循環取引に巻き込むことがあり、逆に、取引先から循環取引に巻き込まれるケースもある(巻き込まれた方も、不適切な売上等が計上されることとなるため、注意が必要です)
(3) 特定担当者への権限の集中
あとで内部統制の問題にも触れたいと思いますが、それとの関係で、循環取引は特定の担当者に権限が集中しているケースが多いとされています。
・営業担当者が受注だけでなく、仕入先選定や商品発注等の発注業務に関与している(通常の職務分掌から外れている場合は注意が必要です)
・担当得意先に対するローテーションの仕組みがなく、同一の担当者が長期間担当している(人事ローテーションが行われていないケースは、循環取引だけでなく、不正が起こりやすい状況として注意が必要です)
・「秘匿性あり」や「業界慣行」等を理由として、一部の担当者しか関与していない(業界慣行は、不正を隠蔽するための理由付けの1つとして多く用いられるとされています)
・特定の限られた役職員以外に、取引内容を理解している者がいない(いわゆるブラックボックス化のケースですね)
(4) 財務諸表上の数字に表れる特徴
一度通常の取引として認識してしまうと発見が難しいとされる循環取引ですが、それでも、財務諸表にはある種の特徴が浮かび上がるようです。
・正常な取引と比較して取引金額が大きいか、取引頻度が高い
・同一商品の販売が多数回繰り返される
・特定取引先に対する取引量が急に増加する(取引開始の経緯が不明瞭であったり、与信限度額の設定変更が行われることにも注意が必要)
・特定の商流において、売掛金や在庫が滞留しているにもかかわらず、仕入が継続している
・一般的な市場価格や販売可能価格と比較して高額な(在庫単価が上昇している)在庫が存在している

3.内部統制による循環取引への対応
企業(経営者)は、不正や誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために必要な内部統制を構築する責任を有しており、循環取引による不正に対しても対応する必要があると考えられます。
先にも述べた通り、循環取引は、一度通常の取引として認識されると発見が困難な取引となる可能性が高いため、発見的統制よりも予防的統制に重点を置くことが重要かつ効果的であると指摘されています。
また、循環取引は、その特徴等からも分かる通り、経営者や内部統制上重要な役割を担う一部の従業員によって意図的に行われる場合が多く、内部統制の限界(内部統制では防止できない可能性)が存在することも指摘されています。しかし、不正の実行は内部統制の不備(=不正の機会につながる)に乗じて行われることが多いことを考慮すると、内部統制の限界を踏まえた上で、不正を合理的に予防・発見するような内部統制を整備・運用することが重要であることも指摘されています。
研究報告では、経営者不正のケースと従業員不正のケースに分けて、企業がどのような対応をとるべきかについて、言及されています。
(1) 経営者不正への対応
経営者による内部統制の無効化という限界は存在するものの、組織内に適切な全社統制及び業務プロセスレベルの内部統制が構築されていれば、経営者が内部統制の不備に乗じて不正を実行する機会は減少すると考えられる
以下のようなコーポレート・ガバナンスの強化も内部統制の無効化への対応策になると考えられる
・適切な経営理念等に基づく社内の制度設計
・適切な職務の分掌
・経営者の内部統制の整備・運用に対する取締役会の監督
・内部監査人の取締役会及び監査役等への直接的な報告の体制整備
取締役会及び監査役等は、経営者が不当な目的のために内部統制を無効化する可能性に留意し、事業上の合理性を念頭に置きながら、循環取引を示唆する状況・兆候が生じていないかどうかを監督・監査することも有効である
三様監査の関係者がコミュニケーションを深め、循環取引の端緒発見の方法や経営者により不正が行われた場合には内部統制の無効化を伴うことが想定されることも議論しておくことも重要である
有価証券報告書の記載内容の適正性や内部統制の有効性の基礎となる重要な事項を想定する中で、循環取引の防止及び適時発見のための内部統制の整備・運用を定め、その状況を個別に確認しておくことも考えられる
(2) 従業員不正への対応
会社の内部統制は、誤謬を防止する観点に重点が置かれ、不正を防止する観点からは十分な整備・運用がなされていないケースや不正発見の機能を十分に発揮できていないケースがある
このため、内部統制の整備状況を評価する際に、循環取引の防止及び発見に資する内部統制が構築されているか、また、構築されている場合に有効に運用されているかを確認することが望ましい
循環取引を発見するための内部統制として、社内外から集められた財務・非財務の情報をもとに、KPIのような指標を設定して継続的に監視し、一定の閾値を超える場合等循環取引の発生が想定されるようなシナリオを立案して、その分析に重点を置いた内部統制を整備・運用することも考えられる
(次回につづく)
あすかコンサルティング株式会社
【会計コンサルティング担当】津田 佳典
プロフィールはこちらをご覧くださいませ!