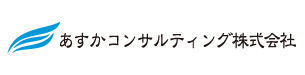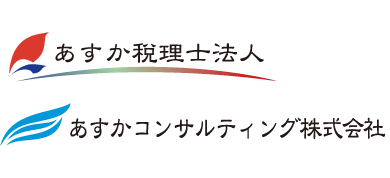BLOGブログ
国際税務2021.11.03 国外関連者に対する貸付金利率に関する裁決事例
過去のブログで海外関連者に対する貸付金の適正利率について記載しました。
資本を超える借入については「過少資本税制」や「過大利子税制」により規制されていますが、国外関連者とのローンについてこのような規制を受けずに通常よりも高い金利を設定することで国外へ利益移転することが可能です。
この問題に対処するため、移転価格税制では独立起業間の金利という考えに基づき「移転価格事務運営要領」において以下のように適正利率の指針を公表しています。
貸付金の適正利率の判定は、下記の順番で行います(移転価格事務運営要領3-8)。
1.借り手が金融機関から通貨・期間等が同条件とした場合に借りるときの利率
2.貸し手が金融機関から同条件で借りる時の利率
3.同条件の状況下で国債等により運用した時に適用される利率の順で行います。
とはいえ実務上は適正利率の算定は困難なため、今回は貸付利率について争われた不服審判所の裁決事例を紹介したいと思います。
1.国税不服審判所 2002年5月24日裁決
税務当局の採用した独立企業間価格の算定方式は採用できないが、銀行が行っている保証の保証料率を比較対象として独立企業間価格を算定するのは、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法であり相当であるとした事例
《要旨》
税務当局は、格付会社が公表する格付け及びデフォルト確率によって納税者が外国子会社に対して行った保証取引及び保証類似取引の保証料率を求め、同料率によって納税者の保証取引等の保証料の独立企業間価格を算定する方法は、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法に当たるので税務当局は相当であると主張し、納税者は、同方法は市場のコンセンサスを得られていたとはいえないので相当でないと主張する。
確かに、税務当局の採用した方法は、審判所の調査によっても審査請求事業年度において金融市場の参加者が保証料率の算定に使用されていたとはいえず、同方法が合理的であるとするに足りる証拠は認められないので採用できないが、銀行が行っている保証取引の保証料率を比較対象として採用して納税者の保証取引等の保証料の独立企業間価格を算定する方法は、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法に該当するので、同方法により算定した独立企業間価格と税務当局の認定した価格との差額を取り消すのが相当である。
納税者がオランダ子会社の発行した債券について行った債務保証に対する保証料率を金融機関の行っている保証料の料率を参考に決定したのに対し、税務当局は米国格付会社が公表する格付け及びデフォルト確率により算定すべきとして争った事例です。
審判所は税務当局の指摘した保証料率の算定について、「金融市場でコンセンサスを得られている」算式というには本件と保証取引と比較可能性の検討が必要であるが、金融市場の参加者が本件算式を用いて保証料を算定したという証拠資料の提示がなく、証券会社や損害保険会社等からも当該算式を用いたという回答は得られていないことから、比較可能性を検討することはできないとしました。
また、納税者の提示する銀行の財務諸表から推計した保証料率の市場実勢は0.15%であり、本件0.1%の保証料率と大きな乖離はないという主張について、当該推計は納税者の行う国外関連取引と同様の状況下で行われたとは言えず、比較対象取引と直ちに採用することは相当ではないとしました。
結果として、審判所が調査したユーロ市場における償還期間や金額等の条件が近似する各銀行の保証取引の保証料率が0.1%であったことから、納税者の用いた保証料率が適正と判断されました。
同種の取引が存在することは稀としながらも、同種の状況下(本件ではユーロ市場)を調査することの必要性が求められた事例です。

2.国税不服審判所 2016年2月19日裁決
国外関連者に対する貸付金利息について税務当局が行った独立企業間価格の算定は相当であるとした事例
《要旨》
納税者は、国外関連者に対する金銭の貸付け(本件貸付け)に係る利息の独立企業間価格について、原価基準法と同等の方法により算定できる旨主張する。
しかしながら、①当該国外関連者は納税者以外の者から借入れを行ったことはないこと、②税務当局は本件各貸付けに係る比較対象取引を把握することができず、当審判所の調査の結果によっても当該比較対象取引を見いだすことができないこと、③納税者からも比較対象取引の具体的な提示がないことから、原価基準法と同等の方法を用いることはできず、他の基本三法と同等の方法を用いることもできない。
そして、金融市場が存在する通貨の貸借取引について、比較可能な取引が実在しない場合には、融資取引の代表例である金融機関による貸付けを基準とすることにも十分な合理性があるというべきであるところ、本件貸付けの貸手である納税者は、本件貸付けの資金を金融機関からの借入れにより調達しており、当該借入れに係るスプレッド情報を得られるから、税務当局が本件貸付けに係る利息の独立企業間価格を独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法である貸手が金融機関から本件貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を用いる方法により算定したことは相当である。
冒頭の「2」貸し手の調達金利が適正利率とされた事例です。
子会社は非関連者である銀行からの借入が存在しなかったため、借り手の調達金利を用いることはできませんでした。
次に貸し手である納税者は子会社への貸付金を取引金融機関より調達しており、この契約金利を子会社との金銭貸借の利率にしていました。
税務当局は金融機関の利率は国際金融市場で示された金利スワップレートに金融機関の利益や事務コストから構成されるスプレッドを加えられていることから、本件においても考慮すべきと指摘をしました。
審判所は貸し手が調達した金融機関の稟議書に記載されたスプレッドを上乗せすることが合理的と判断し、税務当局の主張を認めることとなりました。
3.国税不服審判所 2017年9月26日裁決
納税者の国外関連者に当たる子会社に対してされた米ドルの各貸付けにつき、その利息額の独立企業間価格の算定においては、各米国債の利率による方法が相当とした事例
《要旨》
税務当局は、納税者の国外関連者に該当する子会社(本件子会社)に対して納税者が行った米ドルの各貸付け(本件各貸付け)につき、その利息額の独立企業間価格の算定については、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法である貸手の銀行調達利率による方法(米ドルのスワップレートにスプレッドを加えた利率)によることが最も適切である旨主張する。
確かに、借手である本件子会社には非関連者である銀行等からの借入れの実績がなく、本件子会社が非関連者である銀行等から本件各貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を見いだすことができないことから、借り手の銀行調達利率による方法を採用することはできない。
しかしながら、税務当局が用いたスプレッドは、納税者が本件各貸付けと同様の状況で銀行等から借り入れた場合のスプレッドとして正確性を有するものとは認められず、当審判所の調査によっても他に納税者が非関連者である銀行等から本件各貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を算定する適切な方法を見いだすことはできないことから、貸手の銀行調達利率による方法を採用することはできない。
もっとも、本件各貸付けにおいては、発行日が本件各貸付けの貸付開始日と近接し、発行日から満期償還日までの期間が本件各貸付けの貸付期間に近似する各米国債(本件各米国債)が存在することが認められ、本件各米国債の利率は、本件各貸付けに係る資金を本件各貸付けと通貨、取引時期、期間等が同様の状況の下で国債等により運用した場合に得られるであろう利率に当たると認められることから、本件各米国債の運用利率による方法を採用することが相当というべきである。
冒頭の適正金利算定の「3」を用いた事例です。
この事例では子会社が銀行等の非関連者から借入を行っていないことから参考となる利率が存在せず、貸し手の調達金利として税務当局が提示した金利は貸し手の主要取引銀行から正式に回答を得たものではなく、担当者より参考として入手したものでした。
このことから借り手、貸し手の利率は採用されず、貸付期間と満期償還の期間が近似する米国債が存在したためこの利率が採用されました。
たまたま近似する米国債がありましたが、存在しない場合は金融機関に参考となる金利の資料を依頼し、文書での回答をもらうなど、金利決定の説明が可能な資料整備をしておくべきと考えられます。
いかがでしょうか。どの判例においても誰でも入手可能な形式的な情報により適正利率を判断しているわけではなく、まずは借り手、貸し手の実際の調達金利を重視していることがわかります。
「3」の同条件の国債の利率を用いるには、借り手、貸し手双方の調達金利を入手することが不可能だということを証明することが必要になります。
実務においては金利の決定は慎重に検討し、判断するようにしてください。
あすか税理士法人
【国際税務担当】街 有帆

プロフィールはこちらをご覧下さいませ!