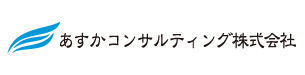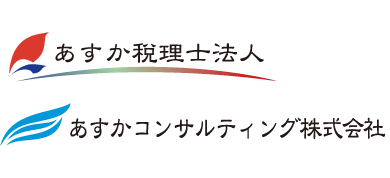BLOGブログ
会計・ファイナンス・監査2018.04.16 収益認識に関する会計基準等の概要①
前回のブログでも取り上げた通り、企業会計基準委員会は、収益認識に関する会計基準等を公表し、平成33年4月1日以降開始する事業年度(平成34年3月期)から適用されることとなりました。今回から暫くの間、この会計基準等の概要について、まとめてみたいと思います。
1.会計処理の考え方
前回のブログのおさらいですが、この会計基準は先に公表されているIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の考え方を基礎としています。
基本となる原則
約束した財・サービスの顧客への移転を、当該財・サービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益の認識を行う。
基本となる原則に従って収益を認識するための5つのステップ
①顧客との契約を識別する。
②契約における履行義務を識別する。
③取引価格を算定する。
④契約における履行義務に取引価格を配分する。
⑤ 履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。
今回は、この5つのステップの中身について、触れてみたいと思います。
2.契約の識別
この会計基準等を適用するにあたっては、次の要件をすべて満たす顧客との契約を識別する必要があります。
①当事者が、書面、口頭、取引慣行等により契約を承認し、それぞれの義務の履行を約束していること
②移転される財・サービスに関する各当事者の権利を識別できること
③移転される財・サービスの支払条件を識別できること
④契約に経済的実質があること
⑤顧客に移転する財・サービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高いこと
①に記載の通り、契約の形態については必ずしも書面で残されている必要はない(口頭や取引慣行も認められている)のですが、会計上の判断過程を明確にしたり、会計監査への対応を考えた時に、今後文書化の必要性がないかどうかを検討しておくことが考えられます。
3.履行義務の識別
契約にける取引開始日に、顧客との契約において約束した財・サービスを評価し、それを顧客に移転する約束を履行義務として識別します。
ここで、複数の財・サービスを顧客に移転する契約となっている場合に、それらを別個の履行義務として取り扱うのか、1つの履行義務として取り扱うのかが論点になります。
会計基準第34項では、「どのような場合に別個の財・サービスと考えるべきなのか?」という点について、以下の2つの判断基準を示しています。
○顧客が、財・サービスからの便益を、それ単独または容易に利用可能な他の資源と一緒にして得ることができるかどうか?
○ある財・サービスを移転するという約束が、同じ契約の中の他の約束と別個に識別できるかどうか?
4.取引価格の算定
取引価格とは、「財・サービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額」ですが、取引価格を算定する際には次の影響を考慮する必要があるとされています。
○変動対価
○契約における重要な金融要素
○現金以外の対価
○顧客に支払われる対価
この中でも「変動対価」については、返品・値引・割戻(リベート)等の要素が含まれるため、多くの企業が影響を受けることが予想されます。
5.履行義務への取引価格の配分
収益の認識は履行義務を基礎として行われるため、算定された取引価格を契約の中で識別された履行義務に配分する必要があります。この配分は、財・サービスの独立販売価格(その財・サービスを単独で企業が顧客に販売する場合の価格)の比率に基づいて行う必要があります。
6.履行義務の充足による収益の認識
収益の認識は、履行義務を充足した時(約束を果たした時)に行われますが、この履行義務の充足は、一時点で充足するケースと一定の期間にわたり充足するケースがあるとされています。
以下のいずれかの要件を満たす場合には、その履行義務は一定の期間にわたり充足される(収益が認識される)こととされています。
○企業が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受する場合
○企業が顧客との契約における義務を履行することにより、資産が生じるか、資産の価値が増加し、それにつれて、顧客が当該資産を支配する場合
○次の要件のいずれも満たす場合
・企業が顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じる。
・企業が顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有している。
これが、収益認識に関する会計基準等の基本的な流れになります。次回は、特定の状況・取引における取扱いが明示されているものをご紹介したいと思います。