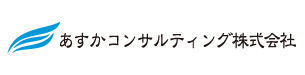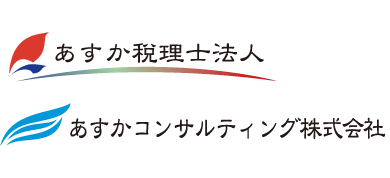BLOGブログ
国際税務国内税務2023.05.11 【国際税務】外国子会社株式評価損~否認事例検討~
前回のBlogで、海外子会社株式の評価損計上が出来るのかどうか検討致しました。海外子会社株式のみならず、売買目的以外の株式について評価損を計上できるケースがあることがご理解頂けたかと存じます。
前回Blogは下記より進んで下さい。
本日は、海外子会社株式に係る評価損計上について、国税より否認されたケースについて、不服審判所での裁決事例(納税者の主張が通らなかった事例)がありますので、その内容を確認することで評価損計上時に注意すべき点をおさらいしたいと思います。

1.背景と経緯
【背景】
・A社(日本法人)はS国に100%子会社のP社(販売業)を設立
・A社は合弁にてS国にR社(製造業)を設立
・R社の業績が悪く、その主な要因はリース料負担(年額2,000千ドル)で、リース料相当額だけ毎年赤字決算
・P社の貸借対照表(資産の部)14,668千ドルのうち、R社株式の帳簿価額は11,100千ドル
・A社は3月決算で、平成18年3月期決算においてP社株式の評価損を計上、税務上も加算留保することなく、損金扱いで申告
・税務調査で上記評価損について否認を受け、異議申し立て→却下、その後不服審判所に対して審査請求
【経緯】
(1)平成17年12月《P社→R社 増資》
P社引き受けによりR社が2,000千ドルの増資を実行しました。(資金は伴わず借入金の資本振替(DES))。
P社からR社に対して2,000千円の出資(増資)です。お金の出入りがないため帳簿上でR社の負債が減り、純資産が増える形です。
これによりR社は単体で債務超過を解消します。
(2)平成18年1月《A社 取締役会》
取締役会にてS国事業の抜本対策案を決議しました。主な決議内容は次の通りです。
・R社負担のリース料が損益面、資金面共に大きな負担である
・リース資産をR社が買取減損処理すれば、資金流出を停止することができ、損益面も改善できる
・12,000千ドル資金注入すればリース契約解約申し出期間中のリース料支払い及びリース資産の買取が可能
・平成17年12月末時点でP社・R社の連結ベースで債務超過状態になるため、P社に対してまず2,000千ドルを先行して払い込み、残額をリース資産買取時期に払い込む
(3)平成18年2月《A社→P社 増資》
A社引き受けによりP社が2,000千ドルの増資を実行しました。
A社からP社へ2,000千ドルの出資(増資)ですね。これは資金の出入りが伴う出資です。この時点でP社・R社連結ベースでは債務超過を解消しています。
(4)平成18年3月《R社 株主総会等》
株主総会及び取締役会を実施しました。主な議事録記載内容は次の通りです。
・R社はリースによる費用及び支出が多額であるため、営業利益やキャッシュフローが赤字になる傾向がある。R社健全化のためには過剰な重荷を取り除く必要がある
→R社はリース契約を解除し設備を買取ることとし、その必要資金10,000千ドルはP社からの増資により捻出する
(5)平成18年3月《P社→R社 貸付》
P社からR社へ1,450千ドル貸付を実施しました。これによりR社はリース料1,562千ドルを支払います。
(6)平成18年3月《A社》
保有するP社株式について評価損を経費処理した上で、税務申告(税務上も損金扱い)。2月に増資2,000千ドル(累計11,500千ドル)した上で、3月に評価損を計上しています。
裁決事例を読み解くと、増資直前に保有していた株式9,500千ドルに対してだけ評価損を計上したようです。
(7)平成18年6月《A社→P社 増資》
A社引き受けによりP社が10,000千ドルの増資を実行しました。
A社はP社株式について評価損を計上した3ヶ月後(翌事業年度)に、P社に対して追加出資した形です。A社→P社への出資額は累計で21,500千ドルです。
(8)平成18年6月《P社→R社 増資》
P社引き受けによりR社が10,000千ドルの増資を実行しました。
A社→P社→R社と10,000千ドルが流れていったイメージです。
(9)平成18年6月《R社》
リース解約及びリース資産買取等として9,566千ドルをリース会社へ支払いました。
(10)平成19年10月《A社》
税務調査により、平成18年3月期に行ったP社株式評価損の否認を受けました。
その後、更正処分内容について納税者は不服があったため異議申し立てを実施、異議審理庁が棄却の異議決定、納税者が不服審判所に対して審査請求を実施しています。
2.納税者の主張
A社はP社株式評価損について否認を受け、不服審判所に対して審査請求します。その内容(納税者の主張)は大まかに次の通りです。
(1)争点1:平成18年3月末においてP社株式の価額の回復が見込まれないと言えるか?
・P社株式価額の回復可能性判断は、事業年度終了時(平成18年3月末)であるから翌事業年度の増資(平成18年6月の10,000千ドル)を含めて判断すべきでは無い
・平成18年2月の2,000千ドル増資は金融機関の強い要請でやむを得ず出資の形をとったが、実質的に「つなぎ資金貸付」であり、この増資にはP社の業績回復に直結する経済効果は無い
・R社によるリース資産買取は、今後も発生するリース料支払いを前倒しで一括支払いしているに過ぎず、S国事業そのものの回復とは別物であり、P社自力による業況回復に直結するものではない
(2)争点2:増資直後のP社株式評価損計上が認められるか?
・争点1で述べたとおり、平成18年2月の増資は実質「貸付け」であり、その点を考慮して判断すべき
・法人税法基本通達9-1-12は増資により業績回復が期待し得るものを想定している場合の取扱いであり、全ての増資に適用される取扱いでは無い。平成18年2月の増資はP社の業績回復に直結する経済効果は無く、法基通9-1-12が想定している増資とは認められない
(3)争点3:増資前のP社株式について評価損計上が認められるか?
・評価損は平成18年2月の2,000千ドル増資前の株式(9,500千ドル)に対してのみ行ったものなので、争点1及び2の主張が認められなくても9,500千ドルに対する評価損は認めるべきである
ポイントは下記三点です。
★ 評価損計上を検討する際に、事業年度末時点において予定されている事柄まで含めて判断する必要があるのか?(予定されていても実行されていないものは含めるべきでは無い、というのが納税者の主張)
★ 増資直後であっても状況によっては評価損を認められるのか?
★ 増資直前の株式と増資分の株式を分けて評価損計上が認められるのか?
3.国税不服審判所の裁決
まず大前提として、上場有価証券以外の有価証券について評価損の損金算入が認められるためには下記①~③の全ての要件を満たす必要があります。
①事業年度終了日における有価証券発行会社の純資産価額が、当該株式を取得した時点の発行法人純資産価額比にして概ね50%以上下回る
②事業年度終了日における有価証券の価額が、同時点の帳簿価額の概ね50%相当額を下回る
③近い将来その価額の回復が見込まれないこと
今回の審査請求では①②については国税サイドも認めているため、③だけが争点となっています。そこを踏まえつつ、各争点について裁決内容を確認します。
(1)争点1
・P社株式価額の回復可能性については、P社の資産状態の悪化が固定的で回復する見込みが無い状態であるか否かの検討が必要
・P社の資産状態にはR社の株式価額が大きく影響する
・P社(販売業)とR社(製造業)の関係性を鑑みて、P社の株式価額の著しい低下有無を検討するためには、R社株式価額の回復可能性検討が必要
・P社株式価額の回復可能性は、将来の回復可能性について判断を行うのであるから、本事業年度終了時までに既に具体的に実行することが決定されていた翌事業年度以降の事業計画等がある場合には、これも含めた上で判断する必要がある
→平成18年1月のA社取締役会議事録、同年3月のR社株主総会議事録等に基づきS国事業の経営改善計画も含めて判断することが相当
・同経営改善計画に基づくと、リース資産買取により平成19年からS国事業は単年度ベースで利益が生じる(資産状態が改善される)ことが見込まれており、審査所の調査でもS国事業の損益計画及びキャッシュフロー計画について不自然なところは無いと判断
→R社の資産状態が改善し、結果としてP社の資産状態も改善される見込み
・P社株式価額の回復が見込まれると判断したのは12,000千ドルの増資により単純にP社の資産状態が改善されることを理由とするものではなく、S国事業に関する経営改善計画の実施(R社によるリース資産の買取)によりS国事業が単年ベースで黒字化することをもって資産状態が改善される方向にあることを理由とするもの
・経営改善計画はR社の経営改善を行うための計画だが、P社の資産状態の改善及び株式価額の回復に直結するものである
(2)争点2
・本件は事業年度終了時点においてP社の資産状態の悪化が固定的で回復する見込みがない状態とは言えないため、法基通9-1-12が適用されるか否かにかかわらず本件評価損を損金算入することは出来ない
そもそも評価損が認められる状態では無いので、この争点について解決はしていない状態です。
なお、法人税法基本通達逐条解説によれば「相当期間は通常少なくとも1~2年をようすると考えられる」とした上で、客観的に明確な事情があれば翌期で評価損を認めるケースもあり得るし、逆に1~2年経過していれば自動的に評価損を認めるわけではない、とされています。
(3)争点3
・評価替えをした資産が有価証券の場合には、事業年度終了時に有する同一銘柄の全ての有価証券について、その評価換え直前の帳簿価額と時価とを比較するものと解される(法人税法第33条第2項及び法人税法施行令第119条の2第1項)
→同一銘柄の有価証券を増資を行う前後で分けて簿価と時価を比較することは出来ないと解される
・P社株式の価額が著しく低下しているか否かを判断するのは、事業年度末に保有していた株式(簿価11,500千ドル)の全ての株式についてとなるので、2,000千ドル増資前の株式についてのみ評価損計上を行うことは認められない
以上により、国税不服審判所は国税サイドの処分が適法であると結論づけました。
4.裁決内容から見える評価損計上時の留意点
如何でしたでしょうか。
原則、法人税は売買目的以外の株式について評価損計上は認められていません。その例外措置として回復が見込まれない場合についてのみ評価損計上が認められています。
「回復が見込まれない」ことはその評価損計上事業年度末時点で想定されている事柄を鑑みて判断することが必要です。事業計画を策定している場合は、その内容を精査して評価損計上の是非を検討する必要があります。
税務調査では「回復が見込まれない」と判断した資料提出を求められることになります。また当該資料と齟齬がある内容の経営会議資料等があれば、それは「回復が見込まれない」とは言い切れなくなる可能性もあります。
事前に資料をよく確認し、計画性をもって評価損計上を実施するようにして下さい。
あすか税理士法人
【国際税務・国内税務担当】高田和俊

プロフィールはこちらをご覧下さいませ。